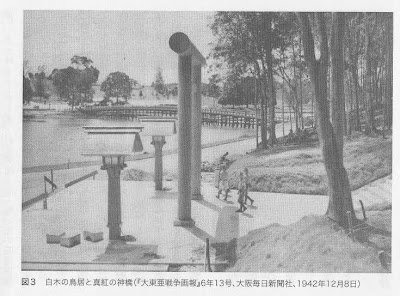さて、「良い時期・良い場所」の話の続きである。前回で、「内部環境における良い時期・良い場所」について、具体的には「自分自身を先ず理解出来た時期に、好きな分野・得意な分野・場所で勝負する事」の重要性について書いた。
今回は、以前のエントリを踏まえた上で、良い時期・良い場所に上手く出くわして幸運を掴むために必要と思われる「準備」について書いてみようと思う。
○「棚からぼた餅」を享受するにも、準備が必要。
今回のエントリで強調しておきたいのは、「棚からぼた餅を享受するにも、準備が必要だ」と言う点である。
良い時期・良い場所に居合わせると言うのは、純粋なラッキーによって為される場合も勿論ある。シンガポール人がただシンガポール人で建国直後にたまたまローンを組んで家を買ったら、みるみる先進国になってゆき不動産価格も高騰して億万長者になってしまったと言う状況がそれに当たる。日本の団塊世代が、日本の右肩上がり時代の経済を享受し、国家財政も微妙であるにも関わらず老後はオイシイ年金を貰って良い暮らしをしているのも概ね同様と考えて良かろう。不況世代からすると内心複雑な思いはあるものの、ただ生まれた時期と場所が良かっただけで人生上手く行く事も実際多々ある。残酷かも知れないがそれが現実であり、人生そう言うものである。
しかし、必ずしも順風満帆ではない時代に生きる我々が「良い時期・良い場所」の僥倖を得ようとなると相応の準備が必要であろうかと思われる。つまり、「棚からぼた餅」を享受するにも、以下のような準備が必要なのである。
・先ず、ぼた餅が落ちて来そうな場所を早期に発見する必要がある(=その1のエントリで記載した「外部環境」の良い場所の発見)。
・かつ、それが自身の能力・適性に合った場所である必要がある(=その2のエントリで記載した「内部環境・個別要因」の良い場所の発見)。
・更に、そこに身を置いた後も、ぼた餅がいつ落ちてきても良いように、皿や箸を準備しておかないといけない。ぼた餅が落ちて来ても地面に落ちてしまったら食べられない。ぼた餅だけでは喉が渇くのでお茶も淹れておく必要がある(=今回のエントリで以下に記載の「準備」に相当)。
こう言った訳で、ぼた餅が落ちてくると言う幸運に、努力・準備が重なって、初めて現代における「棚からぼた餅」は完成するのである(本当の所どうか分からないが、取りあえず勢いでそう言い切っておこう)。
そんな訳で今回は、上記の「棚からぼた餅理論」における三番目、「準備」の部分にフォーカスを当てて、幾らか書いておこうと思う。
○一定の準備段階・下積み時代をきちんとこなす。
先ず重要なのはこの点である。
例えば、自身の身を置く分野で必要な一定の学歴、資格、職務経歴等の確保である。
こう言った要素を馬鹿にする向きもあるし、「実力主義において学歴・資格は関係ない」と言う向きもある。勿論根本的にはトータルに実力が一番重要である。しかし、筆者の経験からすると、そうは言っても現実的な所で言って、ドアオープナーとして・スタート地点に立つために必要な学歴、経歴、資格等は実際あった。こう言う下積み段階・時期を軽く見てはいけないと、筆者自身の経験上は感じている。
例えば、筆者の属する運用業界で、日本においてアナリストなり運用者なりになろうと思えば、大体の場合は早慶程度以上の学歴、証券アナリスト資格位は最低限必要である。一定の学歴が無いと内定も貰えないし、入社後は証券アナリスト資格の取得が運用・調査等の職種への配属条件となっているような場合も多い(証券アナリスト資格やその内容の是非はここでは議論のスコープから外すが、現実としてそうなっている場合が多いと言う事である)。更には外資系大手ヘッジファンドの米国オフィス等では必要条件が一段とインフレートしていて、一流校のMBA(ないしは経済学・理系等でマスターやドクター取得者等)以上の学歴、CFA資格保有、又はこれら複数の経歴保有と言うのが入口として当たり前になっている。米国のグローバルマクロのヘッジファンド等で勤務したい場合、相当ハードルが高い事になる。
勿論、早慶程度以上の学歴があり証券アナリスト資格がありMBAやマスター・ドクターがあればリターンが取れる訳では無いし実力がある訳ではないし優秀な訳でも何でもない。稼げる人も居ればだめな人も多数居る。この点を間違えてはいけない。
また、学歴や資格に関係なく、例えば学生時代からトレードをしていて安定したリターンを出せる手法を確立してそれを投資銀行やヘッジファンドに売り込む事で成功機会を獲得して実際成功した、と言った事例も勿論ある。しかしこのような事例は確率的に言えばかなりレアな部類に属するものであるし、こう言った方法で上手く行く事が出来る人となると、かなり才能・適性等で絞られる面がある。
そんな訳で、運用業界での話で言えば、一般論で言えば、「ドアオープナーとして」「スタートラインに立つために」、最低限これらの経歴・資格はあった方が「良い時期・良い場所」に立てる確率は上がる訳である。
以上では筆者の属する運用業界を喩えにして説明したが、他の分野にせよ、こう言う「スタートラインに立つための準備」と言うのは大概あるものだろうと思う。
法律の仕事がしたいなら弁護士資格を取らないといけない。監査法人で働きたいなら会計士資格が必要だ。料理・食の世界で一流になりたいなら料理学校に行ったり名の通った一流の店で皿洗い・下作業から始めないといけない。ベンチャー企業を立ち上げるにも先ずは大手企業で仕事してスキル・人脈をつけたり大手企業の組織力学、会社員の悲哀の何たるかを学んだりした方が後々良い場合が多いだろう。海外で仕事しようにも、例えば筆者の勤務するシンガポールでは昨今ビザ関連が厳しくなっており、高卒では就労ビザが降りない、ワーキングホリデーの類もいわゆる一流大学出身でなくては活用出来ないものに変更されると言った事態が発生している。商社等で海外事業に配属されるにも、馬鹿馬鹿しい試験だとは思ってもTOEICで高得点を上げないといけない。
学歴コレクター・資格コレクターの類(=学歴・資格自体が目的化している)も馬鹿馬鹿しい話とは思うが、一方で「スタートラインに立つための」「身分証明書としての」学歴・経歴・資格、またこれら獲得のための下積み経験は甘く見ない方が良いと筆者的には思う。こう言うのはまあ、面倒臭いが必要なものなのだと。
こう言う時期を経ないで、例えば大学を卒業して、会社員にはなったが地味な日常が耐えられないからと言った安易な理由で直ぐ退職して、起業ブームやらFXブームやらに煽られて、世間知らずで名刺交換の仕方も怪しいような状態で、言わば半ば躁鬱の躁状態で起業したり専業トレーダーになってしまったような層の「その後」は、惨憺たる鬱々としたものになる事が多いように見受けられる。
勿論これで成功する人と言うのも皆無ではない。しかし、1000社以上上場企業を調べて、中小型株を調べていた頃には未公開企業や新興企業の面々の集まり等にも時折ご縁があった時期も経ている筆者の経験・感覚として、確率的にみてこう言った層がSustainableに成功するのは相当に難しい(下手をすると人並みの生活を維持する事すら難しくなる)ように見受けられる。先ず殆どが失敗してしまうし、一時的に我世の春を享受したものもその後を見ると無残な結果になっている事も少なくない。
一部にはこう言った人でも「起業とその失敗」を売り物にして欧米のMBA等に行き、日本帰国後は先ずは名の知れた投資銀行・コンサル等に戻る事で経済面・社会面ともリカバリーを果たし、次のチャレンジを狙う者も居る(因みに、起業したが失敗した、ちゃんとビジネスのイロハを学んで再チャレンジしたい、と言うのはMBAの志望動機・活用法としては非常に良いと思うし、大学側も評価する傾向が強いように思う)。こう言った人は「起業~失敗、MBA、社会復帰」自体を上手く「下積み経験」として昇華した例だと言えるだろう。次は前回よりは上手くやれるだろう。これは失敗ではなく、有意義な経験と言える。
しかしこれが出来るのは大学学卒時点での学歴が一定以上あり、TOEFLやGMAT等の英語の試験に耐えられ、大学時代に厳しいゼミ等にも参加して起業後も取引先等と真摯にビジネスをやった結果ゼミ教官や取引先等から推薦レターを書いて貰えるような、言ってみれば「意識高く下積み経験を若い頃きちんとやっていた」一部に過ぎない。しかも年齢的に比較的若くないといけない。全体として見れば日本の社会では敗者復活戦は難しい。きちんとした下積みもなく軽はずみにバンジージャンプをした結果、一度人間界から「ナニワ金融道的ワールド」「ニート・職なしワールド」に落ちてしまうと、人間界に戻って来るのも中々難しい、と言うのが全体として見た場合の現実のようにも思う。
きちんとした下積み時代のない人間は周囲からも信用されないし、困った際に助け舟も中々出てこないので、結果として「胡散臭い有象無象」に堕してしまいがちでもある(逆に言えば、地道な下積み時代を経ていて人間的にきちんとしている場合、案外何とかなるケースも少なくない)。
繰り返すが、一定の「下積み時代」と言うのは、大概の分野で、「良い時期・良い場所」の恩恵を(ただの偶然ではなく、低成長経済下で意識して)受けるためには「必要なもの」なのである。
何だよ全然イージーではないじゃないか、何か楽に成功できるような方法論を示してくれないのか、と思われたかたも居るかもしれない。しかし筆者は、その手の「情弱な人々を煽る類の役割」を担う気はない。そう言ったものを求められる方は他を当たって頂ければ幸いである。
○「模索段階・準備段階・下積み段階」を一通り経た位の時期に、「勝負できて成果をきちんと享受できる場所・環境」に居る事。
さて、下積み時代をきちんと積んだら、次はこの、「勝負できて成果をきちんと享受できる場所・環境を獲得する事」が重要である。
これは上記の「地道な下積み」と比べると日本人的美点に訴えづらいと言うか美談になりづらいとでも言おうか、多少あざとい面もあるにはある。
しかしそうは言ってもいつまでも下積みのままでは「良い時期・良い場所」を享受する事は難しい。下積みを開花させるために、Effective、Strategicな形で「次の一歩」を踏み出す必要がある。具体的な手段としては、以下のようなものがあるだろう。
・下積み時代を活かして、良好なビジネスモデルで起業・独立する。金銭面以外でも、一緒に働いていて快いと思えるメンバーで、やりたい仕事が出来ると言った要素を重視する。
・下積み時代を活かして、大手企業からベンチャー企業等に移籍して、ストックオプションや株式等のアップサイドを貰える職務に転職・移籍する。金銭面以外でも、一緒に働いていて快いと思えるメンバーで、やりたい仕事が出来ると言った要素を重視する。
・下積み時代を活かして、固定給過半の職務から、固定給+高比率・好条件の成功報酬・出来高給の職務に転職・移籍・出世なり社内異動なりする。金銭面以外でも、一緒に働いていて快いと思えるメンバーで、やりたい仕事が出来ると言った要素を重視する。
上記は金融業、会社員に留まらずどんな分野でも言えることである。医者も、勤務医、開業医、研究者・教育者、大病院経営、病院コンサル、バイオベンチャー起業等色々な立ち位置を取りうる。料理人も、大手居酒屋の調理から、ホテル料理人、料理屋を作り独立、料理書籍の執筆やセミナー等の色々なアウトプットの仕方と言うか、ビジネスモデルと言うか、立ち位置がある。技術者・研究者等、音楽家や芸術家等も同様である。どう言った立ち位置を取るのか、どういった「マネーフローにおける概念的な場所」に立つかによって、収益の出方等も全く変わって来る。
詰まる所、「良い時期・良い場所」を捉えようとするのであれば、安価な給与で自身の時間を切り売りする立場から、成果・付加価値にが正当に経済的にも報われ、質的にも人生の充実感をきちんと享受出来る立場に移行する必要があり、それはどんな業界や職種でも工夫可能なので柔軟に考える必要があるという事である。以下に、金銭面、質的な面の二つに分けて、この点についてもう少し掘り下げてみたいと思う。
○金銭面で重要な事。
ここで金銭的な面において重要なのは、下請け仕事、時間切り売り仕事から脱出するという事である。
会社員の場合は、上司の下請け仕事・会社に固定給でコキ使われるだけの状態から脱出して、自身の仕事、自身の付加価値に応じた経済的アップサイドのある仕事が出来るようになる必要がある。起業する場合も、規模は小さくとも自身できちんと営業をして受注を取り、付加価値の取れる「元請け」になる必要がある。
つまり個人にせよ企業にせよ、下請け・時給での時間切り売り商売から、月額/年額固定の基本フィー+レベニューシェア・成功報酬、と言ったアップサイドのある「良好なビジネスモデル」「沢山のお金が流れており、個人の付加価値が多く取れる良好な場所」に移動する必要があるのである。
(注:「どんなビジネスモデルが良好なビジネスモデルなのか」と言った点についてピンと来ない方は、普通にキャッシュフロー経営だの競争戦略だのバフェット投資だのの分野を各自勉強して欲しい)。
一般には、企業ブランド・組織・インフラでビジネスが回っており個人の付加価値部分が小さい大手よりも、個人の成果が問われリスクも高い小規模組織の方がこう言った条件は得易い。日系か外資かなら外資の方が解雇リスクもある分こう言った条件は得易い(尤も、昨今は日本企業でも大規模リストラは多発しており、日系なら安泰なのかと言う所は昨今微妙になっており、アップサイドは無くてダウンサイドリスクだらけと言った状況になってしまっている日系企業も見られるようにも感じるが)。
このアップサイドなしに、ただただ我慢と苦労だけを重ねていても、報われるものは少ない。たとえ景気が良く右肩上がりの業界・企業・場所に属していても、言わばマネーフローの観点から見た「自分自身の概念的な居場所・立ち位置」が良好なものでないと、その恩恵をきちんと受けて報われる事が出来ないのである。
これは筆者にも苦い経験があるので、筆者の例で説明しよう。
筆者は2003-2005年ごろの日本株の回復、ライブドアや村上ファンド等に代表されるような中小型株バブルの時に、既に日本株でアナリストをしていたし、正に中小型株の調査を行っていた。中小型株の調査は楽しかったし有意義であった。「100億円部長」と呼ばれ一世を風靡したファンドマネジャーが在籍していた投資顧問会社の他、大量保有報告で賑わしていた中小型株中心のヘッジファンドが投資していた分野と似たような銘柄を筆者も調査してもいた。つまり、「外部環境」「内部環境」とも、この時筆者は「良い時期・良い場所」に居た。棚からぼた餅が降っていたのである。
しかし、筆者はこの時点ではまだ、「準備・下積み」の段階で、「勝負できて成果をきちんと享受できる場所・環境を獲得する事」が出来て居なかった。年齢的にまだジュニアとしての位置づけだった上、比較的大手の運用会社に居たため、筆者個人の立ち位置としては固定給が過半で、出来高給部分が小さかったのである。
筆者の所属していた運用会社も、そのファンド群も大変に儲かった。筆者よりも一回り位年上で、90年代の中小型株投資の黎明期からこの仕事をしていた同業者の先輩の中には、もう働く必要が無いくらい・引退できる位のひと財産を築いた者も少なからずいた。彼ら・彼女らにとっては、90年代の中小型株黎明期の頃から下積み準備をしたものが数年~10年内外の年月を経て遂に花開いた訳であるから、正当な報酬であるし尊敬すべきものだ。
しかし筆者の実入りは引退等とは程遠い、言ってみればジュニアの小遣い程度のものであった。筆者は棚からぼた餅が降っている所に居ながら、皿や箸の準備が出来ていなかった、「勝負できて成果をきちんと享受できる場所・環境を獲得する事」が出来ていなかったのである。このため降って来たぼた餅はむなしくも、はかなくも、悔しくも、情けなくも地面に落下して土と埃にまみれて終わったのであり、これを享受する事が出来なかったのである。今となっては「日本株の、中小型株の調査が専門なんです」等と言っても得られる仕事もない。旬を過ぎれば・祭りが終わればそんなものである(勿論、筆者に関しては今のキャリアに至ったのもこのブログのエントリを書けるに至ったのもこう言った時期・経験があってこそなので、全く無駄だったとは思わないものの、客観的に見れば・言えばそう言う事である)。
得てして「努力はとにかく美徳だ」と言った雰囲気になりがちかも知れないが、実際には「Effectiveに、報われる形で努力する」必要がある。
棚からぼた餅が降っているその時・その場所に、きちんと下積み時代も終えて皿と箸を持ちお茶も淹れておいて、「勝負できて成果をきちんと享受できる場所・環境を整えた状態で」その場に居合わせる必要がある。
そのためには独立したり、大手から名前も聞いた事もないようなベンチャー企業に転職したりする必要がある事も多く、決断とリスクも伴う。これは単に時代や経済の流れを予測出来る知識能力云々とか偏差値・IQが高いの低いの言う話ではなく、人間としての胆力や決断力に関わる話であり、これが結構大変なのだ。勿論、経済・時代の流れや良好なビジネスモデルがどう言ったものか等をある程度読める位の一定の知識・能力は必要な面もあるにはあるが、実際に最後に問われるのは胆力・決断力である。この点に十分な留意が必要である。
○質的な面で重要な事。
また、金銭面以外の面においても、キャリア上のどこかの段階で、一緒に働いていて快いと思えるメンバーで、やりたい仕事が出来ると言った要素を重視する必要があると筆者的には思う。
まず根本的な意味合いにおいて、嫌々仕事をしていては、「良い時期・良い場所」とは言い難いだろう。やっていて楽しいと思えない仕事、人間関係等がギスギスしていても稼げる仕事はあり、金銭的に稼げさえすればそれは「良い時期・場所」と定義出来ると言った反論もあるかもしれない。しかし筆者個人の考えとしては、質的な面も伴ってこその「良い時期・良い場所」であると考える。
また、会社が悪い、上司が悪いと組織や上司、他人のせいにしてしまっているうちは、「自身の仕事」は出来るようにならないようにも思う。仕事の完成度・出来不出来にも影響してくる。踏み込みが甘いと言うか、腰の引けた仕事にどうしてもなってしまう。「会社さえまともなら・上司や同僚がもうちょっとまともなら、俺は/私は本気を出せて、もっと面白い仕事が出来て、成功するはずなのに」等等と自身ではリスクを取らずに評論家風にぼやいて居るうちは、下請け時給労働からは中々脱出は出来ない。ひいては金銭的にも報われる結果にもならない。
本当の勝負は、人間関係も良好で、やりたい仕事もやれる環境が出来て、それに全力投球をする所から始まる。それでも沢山の困難にぶつかるし、ビジネス的に上手く行くか行かないかは分からない、位のものである(筆者も現在、自らの経験としてそれを実感している)。
人間関係等でエネルギーを使っていては建設的な仕事は中々出来るようにならないし、自身はリスクを取らずに評論家風に物事を会社や上司(あるいは日本政府やだめな政治家や日本経済等の外部要因)のせいにしているうちは「良い時期・良い場所」のスタート地点にも立って居ないとも言えるように、筆者個人としては思う。
先ず一歩踏み出して、評論家から当事者になる、必要な所では各自可能な範囲でリスクも取って自分自身がきちんと自分の人生の主人公になる所から、「良い時期・良い場所」への旅路は始まるように思う。
○おわりに
下請け仕事・時間切り売り仕事から脱出する際には、軋轢や周囲の反対もあるかも知れない(特に上司・雇用先企業・今まで自身を下請けとして人月幾らとかコスト+大変薄い利幅等で使っていた元請等からは嫌がられる可能性はある)。
また、大概の場合は大手の安定した企業から外資やベンチャー企業に移籍したり、場合によっては独立したりと言ったキャリア的にもリスクを取った決断を伴う必要があるし、社内で出世等する事により上記を達成する場合も周囲に波風を立てる事を覚悟で何らかのリスクを取る必要があるだろう。自身も迷うかもしれない。また、思いやりのある同僚や友人等は心配するかもしれない。
しかし、「良好な時期・場所」に行こうとなると、恐らく自然と、何らかの一歩を踏み出す必要が出てくるだろう。
一方で、無理して「良好な時期・場所」の幸運を狙いに行かないというのも決して臆病とか軟弱と言う訳ではない。賢明な判断の事も多々あるし、幸せな判断の事も多々ある。実際、リスクテイクして心身・社会的立場等色々壊れてしまった挙句に『異界』行きになってしまうような事例も見られるので、筆者的にはリスクテイク万歳等とは無責任には言えない。そこは各自の価値観に基づく判断による、と言う事になるだろう。
○まとめ
長くなったが、こんな所だろうか。最後にまとめると、「良好な時期・場所」の僥倖を得たいと言うかたは、以下のような準備を重ねる、と言う事になる。
・各自の内部環境・個別要因的に「好きで得意」な有利な分野を、出来るだけ若いうちに試行錯誤して定めておく。
・下積み時代を一定量経る。
・「内部環境・個別要因的に好きで得意」な分野と、「外部環境的に有利な分野」が交差する領域を探す。これは以前のエントリでも書いた通り、単純に成長業界だとか、一般的に人気業界だとかではない。自身が熱意を持って取り組み続けられて、かつ変化率の大きさが狙えそうな場所である。一般には衰退産業と言われていても、意外な所にチャンスがある場合もある。理詰めで探すよりも、「好きで得意」を探求していく中で、直感・感覚に任せた方が見つかる場合も多いように思われる。
・上記交差領域において、取る事の出来るリスクを考える。起業・独立するのが一番ハイリターンだし勇ましいがハイリスクでもある。独立向きでない人、参謀や専門職向きの人、大企業の社内出世や社内起業制度によるスピンオフ等による自己実現の方が合っている人等も居るだろう。「内部環境・個別要因の良い時期・良い場所」に通じる話であるが、自分はどの程度のリスク位までなら取れるのか、と言った要素はきちんと考慮すべきである。
・そして人生の段階において早すぎない段階で決断する(下積みは経た方がいい)。さりとて人生の段階において遅すぎない段階で決断する(住宅ローンで家を買い子供など出来、年齢的にも転職等が難しい年齢になると、勝負に出づらくなる面は確実にある)。
・以上を踏まえて、各自の責任とリスクテイクのもと、「金銭的・質的な面の双方で良い時期・良い場所」の幸運が得られる方向に、慎重に、かつ必要に応じて思い切って、一歩前に踏み出す。
・一歩踏み出した先で根気強く努力と改善を重ねながら、ぼた餅の機会を伺う。
・リスクを取ったものの上手く行かなかったりチャンスを見逃した場合は、人生一休みする、MBA留学等して社会復帰を図る、繋ぎの仕事で何とか食いつなぐ、等等しながら何らかの形でリカバリーを計り、これも学びだと理解して、次のチャンスを伺う。以下繰り返し。
…まあ、何か楽して成功できるような裏技でも何でもないし、こんなの当たり前じゃないか、これを実際やるのが大変なんだよと思われるかも知れないが、全く以って仰る通りである。そこは無料で趣味でやっているに過ぎないブログである。何卒ご理解・ご容赦頂ければ幸いである。
(参考図書)
今回書いたような文章で何か感じるものがあるかた、転職すべきかしないべきか、独立すべきかしないべきか、進路選択をどうしようか、などと考える岐路にあられるかたには、上記書籍を読む事を強く勧める。浅薄に無責任にリスクテイクを勧める訳でもなく、盲目的に安定を重視する訳でもなく、人間ドラマとしての「人生の選択」が生々しく心に響く形で書いてある。何か得る所があるはずである。